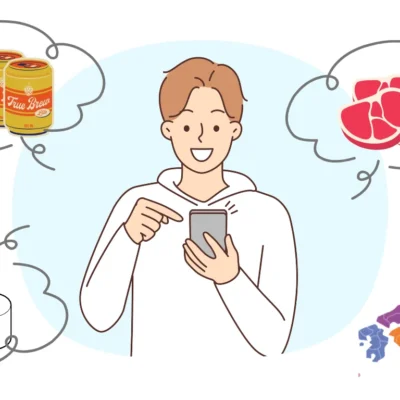08.17

獲る漁業から“育てる漁業”へ ─ しらす漁師が挑む、泉佐野発・車海老の新しい養殖
大阪・泉佐野で長年しらす漁を営んできた現役漁師・濱野栄一さん。
そんな濱野さんが、いま新たに取り組んでいるのが「車海老の養殖」です。
場所は、自社倉庫の中に設けた専用のプール。
天候に左右されない環境で、1匹ずつ丁寧に育てられた車海老は、身がプリッと引き締まり、刺身でも加熱でも驚くほどの甘みと旨みを感じられると評判です。
「自分が食べたいと思えるものしか育てたくない」
そう語る濱野さんの車海老養殖にかける想いとは― 。
しらす漁師が“エビ”に挑む理由──地元の子どもたちにも食べてほしい

お話を伺った濱野栄一さん
― しらす漁一筋だった濱野さんが、なぜ車海老の養殖に?
「地元である泉佐野には昔から“エビを食べる文化”が根づいていて、ジャコエビ(とびあら)を使った郷土料理なんかもあるんです。でも、車海老に関しては、養殖をやっている人がいなかった。だったら自分でやってみよう、と」
「どうせやるなら、泉佐野を代表する新しい特産にしたいという気持ちもありました。“地元ブランド”として、車海老を育てていけたらと思ったんです」
“誰もやっていなかったからこそ、自分がやる意味がある”
そんな想いが濱野さんの挑戦を後押ししました。
― 昔は”漁師は獲るもの”というイメージが強かったですが、変わってきていますね。
「ええ、いまは“育てる”という選択肢もある。どちらも海と生きる仕事には変わりないんやけど、自分の手で時間をかけて育てるっていうのは、また違うやりがいがある」
「毎日の観察や記録を重ねて、少しずつ理想に近づいていく感覚があるんです。目に見える変化もあれば、数字でわかる成果もある。育てるって、思ってた以上に“面白い”仕事やなって思うようになりました」
車海老の養殖は、単なる生産手段ではなく、濱野さんにとって新しい漁師としての生き方そのものとなっているのです。
自社倉庫でゼロから挑戦。目指したのは「安心してうまい」海老

車海老の養殖で使用している水槽
― 最初はどのように養殖を始められたのですか?
「倉庫の中にプールを作って、稚エビを少しずつ育て始めました。最初はほんまに手探りで、水の管理、エサの配合…全部自分で調べながらやりました」
「水の状態ひとつで車海老の味が変わるから、ただ育てるだけじゃダメなんです。『自分が食べるとしたらどうか』って目線で、水質もエサも日々細かく調整しています」
― 試食してみて、手応えはありましたか?
「正直、驚きました。刺身で食べたときの甘みと、身の弾力。これまでいろんな魚を扱ってきましたけど、自分で育てたエビの美味しさには、特別な感動がありましたね」
現在は、毎日の水質検査やエサの配合データを記録し、季節や成長段階に応じた調整を繰り返しているといいます。
「手間はかかるけど、やっぱり“味”で勝負したい。効率よりも品質。それが自分のやり方です」
食べる側の視点を常に忘れない。だからこそ、味・品質・安全性のすべてに自信を持って届けられる一尾が生まれるのです。
― 海に出る漁業ではなく養殖を選択したことに想いなどはありましたか?
海に出る漁業では、どうしても天候に左右されるリスクがつきもの。近年は気候変動の影響もあり、漁獲量の安定が難しくなっているといいます。
「船が出せない日が増えたのも事実。だから、倉庫内での養殖は“第二の柱”として、漁業を続けていくための選択肢になると感じました」
「それに、育てることで“味づくり”にも関われる。自分の理想とする美味しさを、環境やエサでコントロールできるのは新鮮な体験です」
養殖は、単なる漁業の延長ではなく、“ものづくり”としての奥深さを感じさせてくれる仕事。そう話す濱野さんの目は真剣そのものでした。
また、設備投資や維持管理のコストについても現実的な課題として挙げながら、「それでも挑戦する価値はある」と強調。「新しい形の漁師の在り方を模索したい」という想いがにじみ出ていました。
ふるさと納税でも反響続々。「また頼みたい」の声に背中を押されて


出荷前の車海老を保管する冷凍庫
― ふるさと納税での出品を通じて、反響はいかがですか?
「うれしい声がたくさん届いていますよ。『子どもが感動してた』『刺身で食べたら全然違った』『甘みが強くて驚いた』……中には『また同じものを注文したい』とリピーターになってくれた方もいます」
「スーパーで売っている冷凍エビと違って、うちは注文後に新鮮なまま出荷するから、鮮度が段違い。そのぶん手間もかかりますけど、“ほんまもん”を届けたいんでね」
ふるさと納税という仕組みを通じて、全国に濱野さんの車海老が広まりつつあります。
― それだけ良い反響を得るために普段されている工夫はありますか?
養殖の現場では、濱野さん一人の力だけでなく、共に働くスタッフとのチームワークも重要だといいます。
「日々の記録を共有して、変化があればすぐに話し合うようにしています。水温が1度違うだけで食いつきや動きが変わることもあるので、小さな違いを見逃さないことが大切です。」
「毎朝、“今日はこうしよう”って作業の流れをみんなで確認してからスタートする。そうすることで、同じ方向を向いて動けるんです」
スタッフ同士の密な連携が、品質を維持する大きな力となっているのです。
― 最近は外部への発信にも力を入れていると聞きました。
「養殖の現場を実際に見てもらうと、驚かれることが多いですね。透明感のある見た目や、水の中で元気に動く姿って、写真だけじゃ伝わらないんです。」
そのため、見学の受け入れや、SNSでの動画配信なども積極的に行っているといいます。
「最近は、Instagramで水槽の中の様子を配信したりしてます。直接来られない方にも、少しでもリアルな現場を感じてもらえたらと思っています。」
また、地域団体とのコラボイベントなども増えてきており、より多くの人に車海老の魅力を知ってもらう取り組みを続けています。
ただの“エビ”では終わらせない。目指すのは泉佐野の“顔になるブランド”

車海老の養殖槽と濱野さんご一家
― 今後は、どんな展開を考えていますか?
「せっかく泉佐野で育ててるんやから、ブランド化して地元の名物にしていきたい。牛肉や地酒みたいに、車海老を“あの地域の名産”として覚えてもらえたらうれしいですね」
「あと、直販や見学体験の場も作っていきたいです。自分の目で見て、食べて、納得してもらえる“顔が見える食材”って、やっぱり信頼されやすいですし」
漁師としての経験と勘を活かしながら、食べる人の立場を常に考えて水質や環境を整える姿勢。
決して効率や利益だけを求めないその真っ直ぐな姿勢が、一尾の車海老に味として現れています。
編集後記
「自分が食べたいと思えるものしか育てない」―
濱野さんが何度も繰り返したこの言葉には、強いこだわりがにじんでいました。
自分の口に入れて納得できるかどうか。それを基準に車海老と向き合う姿勢に、真摯なものづくりの原点を見た気がします。
“獲る”から“育てる”へ。
泉佐野の海とともに生きてきた漁師が今、未来に向けて新たな一歩を踏み出しています。